ゆかたの着付け
着物はちょっと大げさになってしまうけど、浴衣なら、気楽に着られますよね。
それでも1年に数回、着るか着ないか。
私は去年は一度も着ませんでしたよ。
今年は着るぞ、と思いつつ、このページをアップしました(笑)。
●準備
素肌に直接浴衣を羽織ると、夏の暑さと湿気で、汗だくになってしまいます。本人も気持ち悪いし、周りから見てもあまりいい感じのものではありませんね。せめて1枚、下着を着用しましょう。
スリップとか、シュミーズ(死語?)とか、気楽なものでいいと思います。
きちんとするには、着物用の肌着がありますね。欲を言えば、背中があまり開いてないもの(汗とり)、着物の裾に足が絡まないように、丈が長めの下着がいいでしょう。
ウエストが細くくびれている場合は、タオルを巻いて、補正しましょう。
●着付け
| 1 |  |
2 | 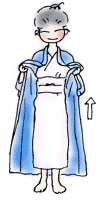 |
|
| 片手で衿の左右をあわせて、もう片方の手で背縫いをつまみ、前後に引っ張り合い(軽い綱引きみたいな感じ)、背中心を決めます。要は左右をずらして着てしまわないようにまず中心をあわせておくということです。 | 衿先から10cmぐらいのところをそれぞれ持って、まっすぐ上に持ち上げます。そのとき、せっかくあわせた背中心をずらさないためには、お尻に布を滑らす感じで、軽く上に引っ張りあげるようにするといいでしょう。 | |||
| 3 | 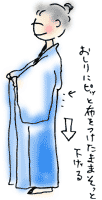 |
4 | 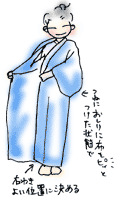 |
|
| 裾をくるぶしの位置にあわせて、丈の長さを決めます。 | 初めに、着たときに上になる方の左の身ごろ(上前、といいます)の位置を決めます。右脇をちょうどいいところにあわせます。このとき、右脇の位置によっては背中心がずれるかも知れません。あまり気にしないでください。 | |||
| 5 |  |
6 | 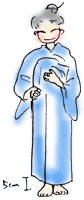 |
|
| 先ほど決めた布の位置をずらさないように、お尻にピッと布をあわせたまま(両手で常に布を前に引っ張っている感じ)、左右の手を入れ替え、右の身ごろ(下前、といいます)をあわせます。 このとき、左脇の下で布がたくさんあまるようなら、奥まで巻かないで、ちょっと折り返して調節しましょう。 下前のつま先を裾から10cm上げて位置を決めます。 |
上前のつま先をすそから5cm上げて合わせ、衿先を右手で押さえ、左手で上前を整えます。しわがいかないように、調節してくださいね。 | |||
| 7 | 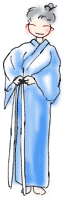 |
8 |  |
|
| 腰紐の中心から15cm位ずらした位置を持ち、短い方を衿先にあて、長い方を左手で左脇まで持っていきます。 | 右手は押さえたままで、左手で紐を持っていく感じです。両脇に手がいったら、そのまま後ろへまわし、後ろで交差して前左よりでひと結びします。 | |||
| 9 | 片花結び |
10 |  |
|
| ひと結びしたあと、片花結びにして、あまった紐の端は後ろにまわしてはさみ込みます。 | 両身八ツ口(脇の下の開いたところ)から手を入れて、後ろのおはしょり(布のあまったところ)のぐちゃぐちゃしたところを整えます。上からトントンと手を下げると、簡単にしわがとれます。 | |||
| 11 |  |
12 | 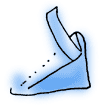 |
|
| 手を前にまわして抱き幅を合わせ、おくみ線(図のまん中の線)の上下がまっすぐ通るように前おはしょりを整理します。 | おはしょりをすっきりさせるために、下前の衿のおはしょりを一重あげします。上前のおはしょりと重なってダボダボしないように、図のように内側に折り返して、すっきりさせるのです。 | |||
| 13 | 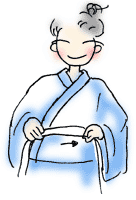 |
14 | 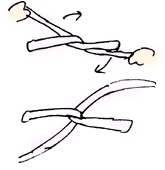 |
|
| 上前の衿あわせをし、胸紐(腰紐を使用)を、胸下より2〜3cm下がったところに当てて押さえます。先ほどと同じように、左手で片方を左脇に持っていき、後ろで交差させて、前の左よりでひと結びします。 | ひと結びしたら、結び目が緩まないように左右を持ち替えてふり分け、両脇の紐にはさんでおきます。 | |||
| 15 |  |
16 | 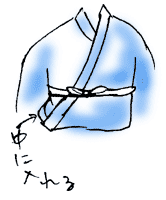 |
|
| 後ろの両身八ツ口を持ち、背縫いが曲がらないように、しわを両脇によせます。 または、図のように紐と着物の間に少し指を入れて、両脇に引き、しわを両脇に寄せます。 |
右脇の余分は前おはしょりの中へ入れて整理し、左脇の余分は、ダーツをとって後ろに倒しておきます。 |
完成

